

ここは敷地の中を公道が通っていて墓域特有の暗さが余り感じられません。歴史のある墓地なのだろうけれど、鎌倉の有名な墓などで感ずるある種の「気」の強さのようなものはないようです。台地の上で水はけが良く日当たりもよい、住宅地にしたいような良好な立地条件もその理由ひとつでしょう。この地を愛好するひとが多いのもうなずけます。

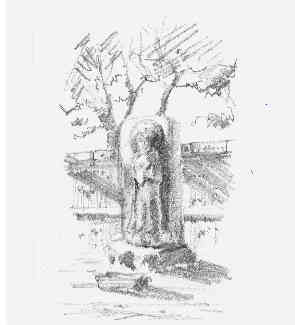





BackNumber p.1 / p.2 / p.3 / p.4 / p.5 / p.6 / p.7/ p.8 / p.9 / p.10 / p.11 / p.12 / p.13 / p.14 / p.15 / p.16 / p.17
/ p.18 / p.19 / p.20 / p21 / p22 / p.23 / p.24 / p.25 / p.26 / p.27 / p.28